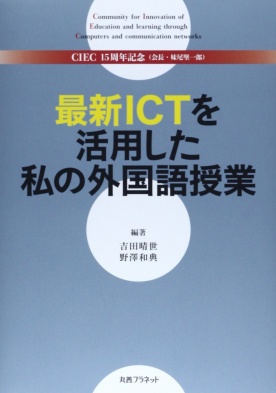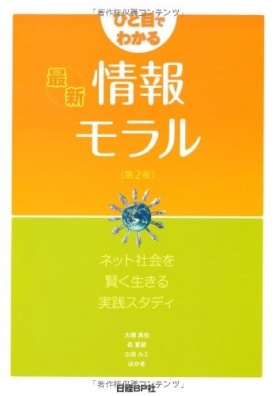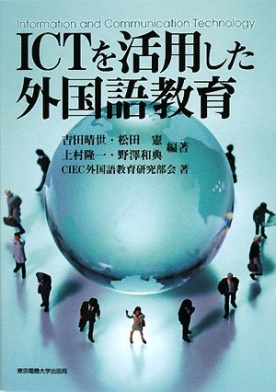定款
2013年6月2日
| 第1条 | 本社団の名称は,一般社団法人CIEC とする。CIEC は " Community for Innovation of Education and learning through Computers and communication networks "の略称であり,「シーク」と読む。日本語訳は「コンピュータ利用教育学会」とする。 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2条 | 本社団は,教育と学びにおけるコンピュータおよびネットワークの利用のあり方等を研究し,その成果を普及することを目的とする。 | ||||||||||||||
| 第3条 |
本社団は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
|
||||||||||||||
| 第4条 | 本社団は,主たる事務所を東京都杉並区に置く。 | ||||||||||||||
| 第5条 | 本社団の公告は電子公告において行う。 | ||||||||||||||
| 2. | 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法による。 |
| 第6条 | 本社団の会員は,個人会員,団体会員とし,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下単に「一般法」という) 上の社員とする。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7条 | 会員は,本社団の目的に賛同して入会を申込んだ個人または団体で,理事会の承認を受けた者とする。 | ||||||||
| 2. | 個人会員及び団体会員は,本社団の事業に参加し,会誌の配布を受け,かつ,本社団の運営に参画する。 | ||||||||
| 3. | 個人会員及び団体会員は,会費を納入しなければならない。 | ||||||||
| 第8条 | 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
|
||||||||
| 第9条 | 退会しようとする会員は,事務局に対して文書によって意思表示し,年度末に退会することができる。ただし,やむを得ない場合はいつでも退会できる。 | ||||||||
| 2. | 会員が本社団の名誉・信用を著しく損ねたときは,理事会の調査による提案にもとづき,社員総会において総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって,除名することができる。この場合,その会員に対して社員総会の1週間前までに理由を付して除名する旨の通知をすることとするが,その除名の通知を受けた会員には社員総会での議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 | ||||||||
| 3. | 会費の長期滞納による資格喪失の手続きについては,理事会において別に定める。 | ||||||||
| 第10条 | 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは,本社団に対する権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。 | ||||||||
| 2. | 本社団は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。 | ||||||||
| 第11条 | 本社団に対し多大な貢献をされた人又は団体について,理事会において名誉会員として選任することができる。 | ||||||||
| 2. | 名誉会員は,本社団の事業に参加することができる。また,会誌の配布を受ける。 | ||||||||
| 3. | 名誉会員は,会費を免除される。 | ||||||||
| 第12条 | コンピュータ利用教育の発展・普及に大きく寄与,あるいは本社団の活動において大きな貢献をした個人会員または団体会員に対し表彰をすることができる。表彰規程は理事会において別に定める。 |
| 第13条 | 本社団には次の役員を置く。
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 前項第一号の理事の中から,次の役員を選任する。
|
||||||||||||
| 第14条 | 会長理事及び副会長理事をもって本社団の代表理事とする。 | ||||||||||||
| 2. | 会長理事は,会務を統括する。 | ||||||||||||
| 3. | 副会長理事は,会長理事を補佐し,会長理事に事故があるときは,その職務を代行する。 | ||||||||||||
| 4. | 前項において,会長理事の職務の代行は,会長によって指名された副会長理事が行う。 | ||||||||||||
| 第15条 | それ以外の理事は,会長理事の総括のもとに会務を行う。 | ||||||||||||
| 第16条 | 監事は,次に掲げる職務を行う。
|
||||||||||||
| 第17条 | 理事及び監事は,社員総会において選出する。 | ||||||||||||
| 2. | 会長理事,副会長理事は理事会において選任する。 | ||||||||||||
| 3. | 監事は,本社団の理事もしくは使用人を兼ねることはできない。 | ||||||||||||
| 第18条 | 理事及び監事について,当該役員及び当該役員の配偶者又は三親等以内の親族その他特別の関係にある者の合計数は理事の総数または監事の総数の三分の一を超えてはならない。 | ||||||||||||
| 第19条 | 理事および監事の任期は,いずれも2年とし,再任を妨げない。 | ||||||||||||
| 2. | 補欠または増員により選任された役員の任期は,その選任時に在任する役員の任期の満了する時までとする。 | ||||||||||||
| 3. | 役員の任期の終了期限は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 | ||||||||||||
| 第20条 | 理事及び監事は,無報酬とする。 | ||||||||||||
| 第21条 | 役員選挙に関し必要な事項は,法令またはこの定款に定めるもののほか,社員総会において定める役員選挙規約による。 |
| 第22条 | 本社団には,議決機関として社員総会を置く。 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 社員総会は,会長理事が招集する。 | ||||||||||||||||
| 第23条 | 社員総会は,第7条に定める会員をもって組織する。 | ||||||||||||||||
| 2. | 社員は,各一個の議決権を有する。 | ||||||||||||||||
| 第24条 | 社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会とする。 | ||||||||||||||||
| 2. | 定時社員総会は,毎年1回,毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。 | ||||||||||||||||
| 3. | 臨時社員総会は,会長理事が必要と認めた場合,又は10分の1以上の会員から議事を示して請求のあった場合開催する。 | ||||||||||||||||
| 4. | 前項の会員からの請求による臨時社員総会については,会長理事は請求のあった日の翌日から起算して30日以内に開催しなければならない。 | ||||||||||||||||
| 第25条 | 社員総会は,一般法に規定する事項並びにこの定款に定める事項に限り議決する。 | ||||||||||||||||
| 2. | 社員総会は,次の事項を議決する。
|
||||||||||||||||
| 第26条 | 社員総会の議事の内容は,あらかじめ社員に通知されなければならない。 | ||||||||||||||||
| 第27条 | 社員総会は,総社員の3分の1以上の出席により成立する。 | ||||||||||||||||
| 2. | 前項の,社員総会への出席とは,本人出席,書面ないし電磁的方法による出席,委任出席とする。 | ||||||||||||||||
| 第28条 | 社員総会における決議は,出席者の過半数の同意を要する。 | ||||||||||||||||
| 2. | 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
|
||||||||||||||||
| 第29条 | 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。 | ||||||||||||||||
| 2. | 議長及び出席した会長理事,副会長理事は,前項の議事録に記名押印する。 | ||||||||||||||||
| 第30条 | 社員総会の運営に関し必要な事項は,法令またはこの定款に定めるもののほか,社員総会において定める総会運営規約による。 |
| 第31条 | 本社団には,執行機関として理事会を置く。 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 理事会は,すべての理事をもって組織する。 | ||||||||||
| 3. | 理事会は,必要ある場合,構成員以外の者の出席を認めることができる。 | ||||||||||
| 4. | 理事会は,必要ある場合,特別委員を委嘱することができる。 | ||||||||||
| 第32条 | 理事会は,会長理事が招集する。 | ||||||||||
| 2. | 理事会は,毎事業年度4回以上開催する。 | ||||||||||
| 第33条 | 理事会は,次の職務を行う。
|
||||||||||
| 第34条 | 理事会は理事の総数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 | ||||||||||
| 2. | 理事会の議事は,理事会は議決に加わることのできる理事の総数の過半数が出席し,その過半数をもって決するところによる。 | ||||||||||
| 3. | 理事会の議事は,その議決について議決に加わることのできる理事の全員が,書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。なお,監事が異議を述べたときは,この限りではない。 | ||||||||||
| 第35条 | 理事会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成し,出席した理事及び監事は,これに記名押印する。 |
| 第36条 | 本社団には,第3条に定める事業を遂行するため,専門委員会を置くことができる。 |
|---|---|
| 2. | 専門委員会の組織及び運営に関する規則は,理事会において別に定める。 |
| 第37条 | 本社団には,支部および部会を置くことができる。 |
|---|---|
| 2. | 支部および部会の運営・事業等に関する規則は,理事会において別に定める。 |
| 第38条 | 本社団には,事務局を設ける。 |
|---|---|
| 2. | 事務局長は,副会長理事の1名が兼務する。 |
| 3. | 事務局員は,会長理事が理事会の承認を得て任免する。 |
| 4. | 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は,理事会において別に定める。 |
| 第39条 | 本社団の経費は,会費,協賛金,寄付金及びその他の収入をもって支弁する。 |
|---|---|
| 第40条 | 本社団の会計年度は,毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終る。 |
| 第41条 | 本社団の事業計画書,収支予算書については,理事会の議決を経て,社員総会の承認を受けなければならない。 |
| 第42条 | 本社団の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,監事の監査を受けた上で,理事会の議決を経て,社員総会に報告し承認を得なければならない。 |
| 第43条 | 本社団の会計は,一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。 |
| 第44条 | 本社団は剰余金の分配を行わない。 |
| 第45条 | 本社団を解散したときは,その残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国に贈与するものとする。 |
| 第46条 | この定款に定めるもののほか,本社団の事業及び運営に必要な事項は,理事会において別に定める。 |
|---|
| 第47条 | 本社団の設立初年度の事業年度は,本社団成立の日から平成25年6月30日までとする。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第48条 |
本社団の設立時役員は,次のとおりです。
設立時役員の任期は,本社団の成立から2013年度定時社員総会終了時までとする。 |
||||||||||||
| 第49条 |
設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりです。(住所略)
|
||||||||||||
| 第50条 | 任意団体CIECに属した権利義務の一切は,本社団が継承する。 |
以上,一般社団法人CIECを設立のため,定款作成代理人である司法書士法人A.I.グローバル (代表者社員 上野興一)は,電磁的記録である本定款を作成し,電子署名する。
平成25年6月2日
| 1 | この定款は2014年8月9日,一部改定を実施した。 |
|---|