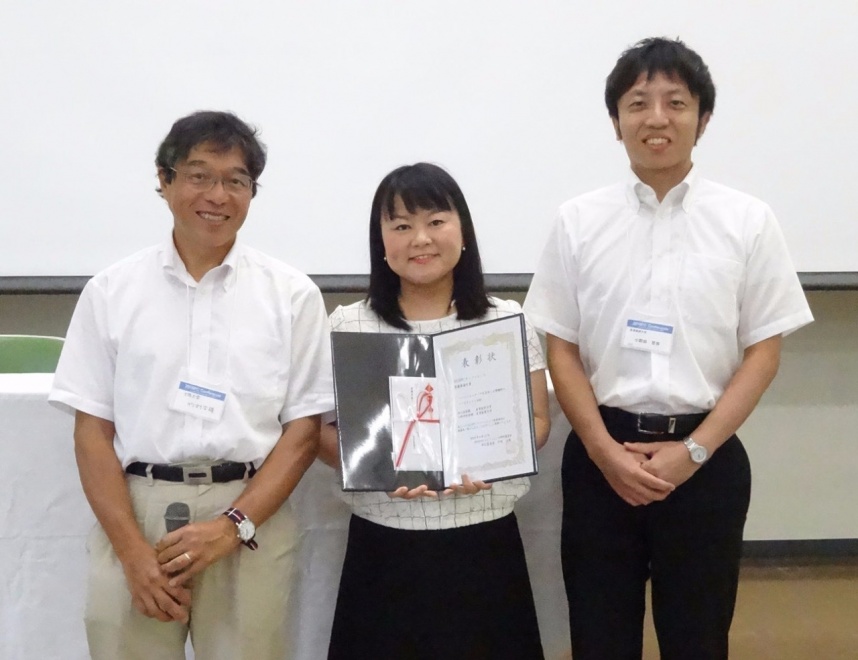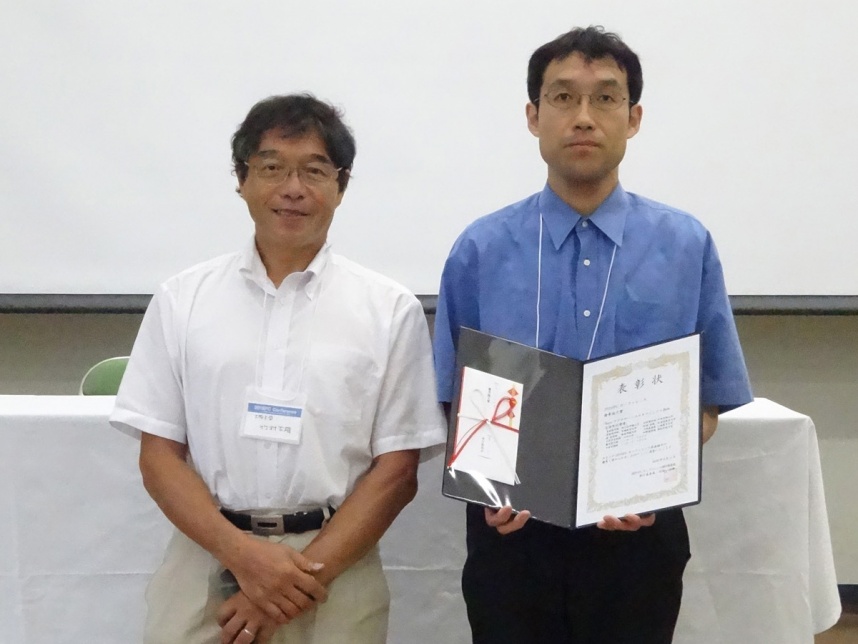第6回 2016年度学会表彰 ―受賞者喜びの声―
2016PCカンファレンス開催中の8月11日(木)、CIEC総会会場において「2016年度CIEC学会賞」の表彰式が行われました。Special第6回では、表彰式にて賞状と副賞を授与された受賞者の皆さんの「喜びの声」をお伝えします。
2016年度CIEC学会賞論文賞
澤口隆(東洋大学)・巽靖昭(久留米工業大学)
「バックグラウンド稼働クリッカー(bgClicker)の開発」(『コンピュータ&エデュケーション』Vol.38,2015.6)
澤口 隆 (東洋大学 経済学部 教授)
この度はCIEC学会賞論文賞という大変名誉ある賞を受賞させて頂き、光栄に存じます。日本の教育現場でクリッカーが利用されるようになって10年近くが経過しました。スマートフォンを利用したクリッカーも数多く開発・公開されています。あるセミナーで実際に受講生の立場でクリッカーを利用した際、受身の意思表示だけではなく、「もっと様々な意見をクリッカーを使って自由に講師に伝えたい」と思った経験から、“bgClicker”を開発致しました。大人数教室での双方向授業が実現できるだけではなく、 “bgClicker”のログデータを分析することで、授業のどこで学生がつまずいているかなどが可視化され、授業改善に生かすこともできると考えています。
巽 靖昭 (久留米工業大学 共通教育科 准教授)
この度は学会賞論文賞という名誉ある賞をいただき、大変嬉しく思っております。学修者の能動的な学びが求められて久しいですが、大学教育の場では100人を超える大人数講義もまだまだ存在し、その中で教員と学修者の双方向意思伝達は、我々教員にとって大きな課題です。この研究がどなたかの目に留り、どこかで授業改善の小さなタネとなれば、この上ない喜びです。この受賞を励みに今後も教育現場に於ける様々な課題に取り組んでいきたいと考えています。
2016PCカンファレンス最優秀論文賞
白土由佳 (産業能率大学)・小野田哲弥(産業能率大学)
「ソーシャルメディアを活用した業種別のワークスタイル分析」
白土 由佳 (産業能率大学 経営学部 専任講師)
このたびは大変光栄な賞をいただき、ありがとうございます。本研究のきっかけは、キャリア教育に注力している産業能率大学に入職したことでした。私自身は、社会学やライフスタイルを専門としており、当初、キャリア教育とは距離を感じておりました。しかし、小野田先生がご自身の専門であるロングテールマネジメントを「知られざる優良企業の発見」で活かしていることに学び、私自身も専門性を活かしキャリア教育に貢献したい、と研究に取り組み始めました。毎年のPCカンファレンスにて、報告に対するご指導やディスカッションを下さった皆様のおかげで、本研究はユニークに育ってきたと感じます。皆様に育てていただいている本研究を、より大きく発展させ、CIECおよびキャリア教育に貢献していけるよう、引き続き努力して参ります。
小野田 哲弥 (産業能率大学 情報マネジメント学部 准教授)
本研究は2011熊本大学PCCにて優秀論文賞をいただいた「知られざる優良企業の発見」の発展版です。当時の優良企業の定義は、有価証券報告書の「財務データ」に基づいていました。しかし“優良企業の定義は人それぞれ”というキャリア教育の原点に立ち返り、本研究では各学生が自分のものさしで優良企業を探すことができるように「ワークスタイル」で企業を類型化しています。分析に用いたリソースがSNSだという点でも、ここ5年間のメディア環境の変化を象徴しているかと思います。白土由佳講師は、2011年当時はまだ大学院生でした。その後同僚となり、ソーシャルメディア専門家としての知見を如何なく発揮して、本研究を大いに発展させてくれたことに敬意を表します。そして5年前、まだ発展途上だった本研究に対し、期待を込めて優秀賞を授与してくださったCIEC関係の皆様に、あらためて御礼申し上げます。ありがとうございました。
2016PCカンファレンス優秀論文賞
鳥居隆司(椙山女学園大学)・田村謙次(中央学院大学)・安藤明伸(宮城教育大学)・杵淵信(北海道教育大学)・森夏節 (酪農学園大学)・川崎直哉(上越教育大学)・大岩幸太郎(大分大学)・中野健秀(愛知学院大学)・藤尾聡子(シンカーズ・スタジオ)・古金谷博(シンカーズ・スタジオ)
「Webブラウザベースのオブジェクト指向言語実行環境」
鳥居 隆司 (椙山女学園大学 文化情報学部 教授)
この度は、「2016年度 PCカンファレンス論文賞」を頂き、誠にありがとうございます。このような賞を頂けるとは全く思いもよりませんでした。また、本論文作成に関わっていただいた共著者の方々にも心より感謝いたします。本研究では、プログラミングの学習環境の構築が困難で、プログラミング学習以前に挫折してしまう状況を改善する目的で、極めてシンプルにプログラミング学習を始めることができるように考えております。最近になって、プログラミング教育の重要性についての話題が多くみられるようになってきましたが、情報教育では、ソフトウェアの使い方について多くの時間が割かれてしまっていることも事実です。GUIに優れた情報環境が当たり前になってきたことで、コンピュータのブラックボックス化が進み、情報を科学的に理解しにくい状況が進行しているように思いますが、この受賞を励みに、これからも頑張っていきたいと思います。
2016PCカンファレンス学生論文賞
森田賢太(東海大学)・栗原恵莉奈(東海大学)・森田直樹(東海大学)・高瀬治彦(三重大学)
「視覚障害者の学びを支えるための物体認識システムの構築」
森田 賢太 (東海大学 情報通信学研究科 情報通信学専攻)
この度は、学生論文賞に選んで頂き、大変嬉しく思います。まずは、選考していただいた先生方に感謝いたします。僕がCIECに参加したのは、昨年からでした。その年に、最優秀論文賞の発表を聴講して、学生でも最優秀賞を受賞できるのだと感銘をうけ、自分も賞を受賞したいと思い頑張った結果、想像より早く受賞できましたので驚いています。自分の研究を発表するだけでなく、他の人から選んでいただけるというシステムはとても研究や発表に対してモチベーション向上に繋がります。今後は、この成果をさらに発展させ論文として投稿したり、さらなる教育効果向上のためにコンピュータの利用の仕方を模索したりしていきたいと思います。
受賞者の皆さん、おめでとうございました!!