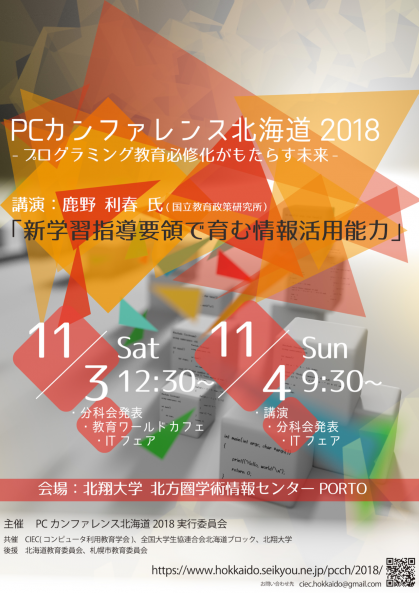執筆要綱
2018年8月25日改正
原稿は(「本の紹介」以外)所定のサイトにてアップロードしてください。
原稿は編集委員会が必要と判断した場合, 表現方法等の記述変更をお願いする場合があります。
既発表論文, 他誌への掲載済みの論文については著作者があらかじめ版権と本誌への掲載許可について承諾を受けてください。
I 執筆についてのお願い
1 原稿について
執筆にあたっては,本ページの下部にあるページ数確認用テンプレートを参照してください。アクセスすることができない場合は,CIEC事務局に問い合わせてください。
2 本文以外の体裁および文字数について
別途定めます。
3 題目・概要などの記述について
「研究論文」・「実践論文」および「研究ノート」・「実践報告」
以下の 6 項目を和文と英文で記述をお願いします。
- 表題 (title)
- 副題 (subtitle)
- 著者 (author)
- 抄録 (abstract):英文はネイティブチェックをお願いします。
- キーワード (keyword)
- 連絡先 (contact)
ソフトウェアレビュー
以下の 5 項目を和文または英文で記述をお願いします。
- 表題 (title)
- 副題 (subtitle)
- 著者 (author)
- キーワード (keyword)
- 連絡先 (contact)
4 図版を挿入する場合
4.1 図は原稿とは別にデジタルデータを所定のサイトからアップロードしてください。図のファイル名は, 本文中と同一の図番号を用いてつけてください。(例:Fig1.bmp)
4.2 図をWord, Excel, PowerPoint で作成した場合は それぞれの標準保存形式で(使用フォントは, MS 明朝, MS ゴシックのみ), それ以外の場合は JPEG(最高画質), BMP, PNG, TIFF のいずれかの形式でお願いします。
5 校正
5.1 原則として,著者校正は初校のみとし,再校以後は編集委員会で校正します。
5.2 初校の校正では,DTP 上での誤りや不備を訂正することを重点とし,原稿を改訂することはご遠慮ください。
6 詳細規定
その他, 詳細については編集委員会で統一的用法に変更することがありますので一任願います。
II 原稿作成要領
1 表記法
1.1 横書き,新仮名つかい,新字体使用を原則とします。当用漢字を中心とし,旧漢字などは極力避けてください。また,国文学関係の論文も「横書き」を原則とします。その際,漢詩など縦書きが必要なものが出た場合は図版扱いでお願いします。
1.2 句読点は,和文の場合は,全角カンマ(,)およびマル(。)を使用してください。
1.3 引用文にはカギ括弧(「」,『』)を使用してください。
2 章だての書き方,表,図の番号
2.1 章だての書き方
- プレフィックスラベルの書き方は_リーガル書式_でお願いします。 ex) 1, 1.1, 1.2,・・・, 2, 2.1, 2.1.1,・・・, 3, 3.1 ,3.2, ・・・
- 図の見出しは, Fig.n キャプション にしてください。 ex) Fig.6 CIEC体制図
- 表の見出しは, Table n キャプション にしてください。 ex) Table 7 CIEC年表
3 数字
3.1 原則としてアラビア数字。半角でデータを入力してください。
3.2 熟語や固有名詞は和数字
3.3 経済学等で慣用となっている場合はローマ数字
3.4 概数の場合は和漢字
4 注(end notes)と参考文献(reference)について
4.1 注は本文末に,参考文献も含めて列挙し,本文中の当該箇所右肩に通し番号を打ってください。
4.2 執筆にあたって,参考とした文献があれば「参考文献」に含めてください。
5 参考文献
5.1 単行本,雑誌名は,和文の場合は『』で囲み,欧文などはイタリックにしてください。
5.2 論文名は,和文の場合は「」,欧文などは“ ”で囲んでください。
5.3 文献の表記は次の順序で行ってください。 単行本:著者(編者)名,著書名,発行所名,発行年。 論文:著者名,論文名,雑誌名,巻数,号数,発行年月日,頁数
5.4 URL (Uniform Resource Locator) アドレスを参照する場合の記述形式は,著者,表題,URLアドレス,参照日の順とする。