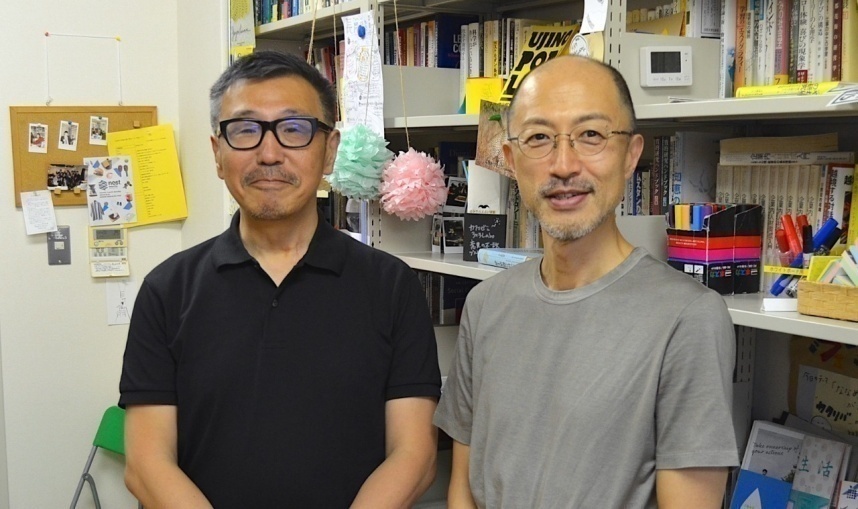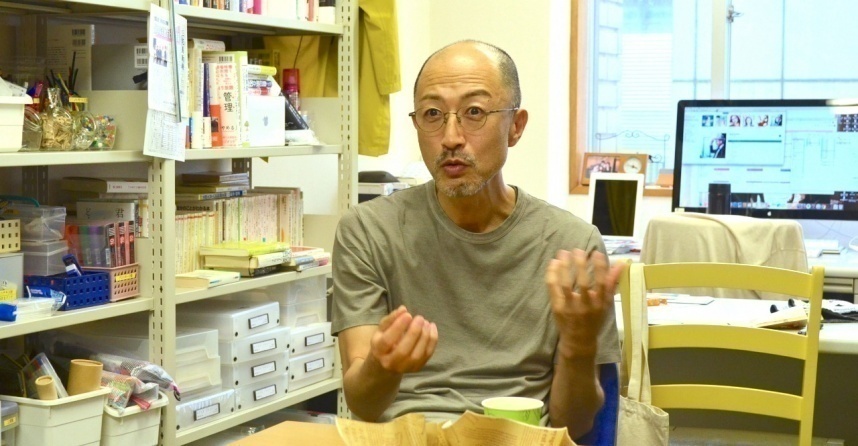Special第20回「剽窃チェックサービス『Turnitin』が守る教育と研究の信頼」を公開しました
Special第20回は、「剽窃チェックサービス『Turnitin』が守る教育と研究の信頼」をお送りします。ぜひご覧ください。
2013年8月4日制定 総則 第1条 この会の社員総会における役員 (理事・監事) の選挙はCIEC定款第13条から第21条に基づき,この規約の定めるところによってこれを行う。 選...
2013年6月2日 総則 第1条 この規約は,CIEC定款の第22条から第30条までの規定にもとづき,社員総会の運営について定めるものである。 2. CIEC定款およびこの規約に定める...
CIEC著作権規程 (目的) 第1条 本規程は、一般社団法人 CIEC(以下「本社団」と略記する。)に投稿される著作物に関する著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。なお、...
設立総会議事録 日時 1996年7月6日(土) 17時20分〜18時30分 場所 稲田大学理工学部57号館201教室 司会者、松本朗設立準備委員会運営委員 (愛媛大学教員) が、17時20分、...
PC カンファレンスとは PCカンファレンスは CIEC 誕生の源です。CIEC 設立後は全国大学生協連とともに主催し、学会にとって重要な研究交流のための年次集会として発展し...
2023PCカンファレンス 開催地つくば国際会議場 全体テーマ変わる社会、変わる学習環境 発表一覧2023論文集 2022PCカンファレンス 開催地オンライン 全体テーマ学びの...
記録映像 設立総会 (1996年7月6日) 1本 通常総会 (1997年8月5日) 1本
第1条本規定は、CIEC(以下,本会と略記する)会長が所有する著作権について定め ることを目的とする。 第2条対象とする著作物には次のものがある。 一会誌『コンピュータ&...
小林昭三 (新潟大学・教育人間科学部・理科教育研究室) 理科教育におけるJava実演集 UNIXサーバ構築記録集 中村泰之 (名古屋大学・情報科学研究科) シミュレーション物...
コンピュータ&エデュケーション 『コンピュータ & エデュケーション』は CIEC 唯一の公式学会誌です。 企画・編集は会誌編集委員会が担当しています。...
Special第20回は、「剽窃チェックサービス『Turnitin』が守る教育と研究の信頼」をお送りします。ぜひご覧ください。
剽窃チェックサービスとして世界的なシェアを持つ「Turnitin」(ターンイットイン)を導入する教育機関が近年国内で増加傾向にある。そこで、国内の代理店であり、CIEC団体会員でもあるiJapan株式会社を取材し、Turnitinの機能や活用事例などを伺った。
先日スタートした「会長がインタビューする企画」ですが、第1回の熊坂賢次さんに続き、第2回の長岡健さんの記事が公開となりました。
会長インタビュー#2 長岡健さん
https://www.ciec.or.jp/special/entry-1207.html
今回は「越境と学習」をテーマに、大学生が越境とどう向き合っているかや、長岡さんのゼミではPBLやアクティブラーニングをしない理由など、今の時代の教育環境を捉えた興味深い内容になっているかと思います。
ぜひご覧ください。ソーシャルでのシェアなども大歓迎です。
CIECの会長自らが、CIEC会員を中心にユニークな研究や実践に取り組む方々をインタビューするこの企画。第2回は、CIECの元副会長であり法政大学経営学部教授の長岡健さんにお話を伺いました。
編集・注釈 : CIEC広報・ウェブ委員会 角南北斗
写真 : CIEC広報・ウェブ委員会 小野田哲弥
インタビューは、長岡健さん (右) の研究室で行われました。左はインタビュアーの若林靖永CIEC会長です。
このあいだ、とある企業の社内誌に何か書かないかって言われて。「どれぐらい?」って聞いたら「3,000字ぐらいの」と。それで引き受けたら、3,000字しか書かないのに、読んだ人の行動が変わるようなすっごく良いことを書いてくれという話になって。
本一冊読んだって変わらないのに、それはちょっと無理があると思うんですよね。だって、ウェブ配信の3,000字のコラムっていったら、読むのは電車の中ですよ。それで変わったら苦労しないよなぁと思ったんですけど、頑張って書きました。
まぁでも変わる時はボリュームじゃないよね。10文字でも変わってしまう人は変わってしまうので。
本当にこれは状況の話で、どういう状況の時に出会うかで関わり方が違うので。たとえたくさん書いても、その人の置かれてる状況、その人が準備できてないと変われない。変わる・変わらないっていうのは、いま子育てしてて本当に思うけど、こっちがこういうふうに仕向けたらこうなる、などとプログラミングできない。
そう思います。今日のテーマである「越境」にもたぶん関係してるんですけど、さっきの話はビジネスの人なんで、やっぱり学習のイメージが「熟達」とイコールな気がするんですね。熟達って (学習の) ほんの一部なんだけれども、やっぱりビジネスマンが (学習に対して) イメージしてるのは熟達なんで。ある方向にまっすぐ垂直的に伸びていくとか、能力が上がるっていうのが学習だと思ってるから。
そこに境界を考えてないよね。
熟達も、狭い境界での熟達を考えるか、それとも、MBAの教育なんかそうですけど、複数の部門とか部署とかファンクションを越えたメンバーとか、相手先企業との共同コラボレーションとか、そういうところでの熟達って話になると、ストーリーが変わるんだよね。明らかにその境界を超えないといけないから。だから熟達っていうときに、狭い意味での熟達と、境界を超えて行動できる熟達は、かなり意味合いが違う。そこのところを (自分で) ちゃんと自覚できてるかが大事じゃないかなと思うんですけどね。
熟達のイメージが境界を超えない狭いものになるのって、いまのビジネスマン、学生もそうなんですけど、ゴールが明確であってまずゴールを知りたい、目標地点が自分で納得できるシンプルでわかりやすいものじゃないと、動けない気がするんです。
そうすると必然的に、いろんなコラボレーションの結果、新しい融合領域で何かが起こるっていうのは、起こったあとのイメージが (事前に) なかなかしづらいので、彼らはそういうものを学習のゴールとしない気がするんですね。
つまり、今の段階で「学習した・成長した後の自分がこうなってるというイメージ」が明確に担保される、確信できる方向にしか、動きたがらなくなってるという気がしますね。
そこは本当に、私の両親世代と今の若い人たちとの大きな違いで。やることの意味、自分にとってプラスになる・ならない、みたいなところでの納得感がないと動けない。
はい、はい。
私の両親に聞いてみると、そんなこと考えてないわけよ。状況の時点で全力を尽くしてる。しかも、その全力を尽くすっていうのは、その場のメンバーシップ、メンバーとして頑張ることなんだよね。
だからどっかの仕事に就いたら、その仕事の世界の職場の中で、他の人のことを参考にしながら、そこで自分の最大の努力をしてメンバーの中で役割を果たす、と捉えられてる。ある種、共同体の目的と自分の目的が結果的にイコールになるってことなんだけど。自分にとって利益になるか・ならないかっていうような目的がほとんど出てこないんだよね。もちろん、出世したいとか、企業内部でのいろんな動機付けはもちろんありえるから、ゼロとは言わないけどね。でも基本、目的について「自分にとってプラスになる」っていうところでの合意がなくても動けるんだよね、昔の人は。
今の人はそこを「これはこういうふうに得なんですよ」「こういうふうにあなたにとって役に立つんですよ」と、お店で物を買うようにしか行動ができなくなってる。ある意味、消費的なんだよね。買い物的っていうか。
でも、それはすごくロジカルで。きちんと意味づけをしなさいとか、ものを考えて吟味して論理的なプロセスを経て答えを出しなさい、っていうのが染み付いている。それは、ある意味教育の成果だっていう気もするんですね。
この間、就職サービス系の企業の人と話をしてたら (今の学生は) 就職を決めるのも極めてロジカルだって。昔の人に比べて一人あたりの内定数が増えてるって言うんです。なんでかっていうと、最初に自分の希望を決めるっていうプロセスじゃないんだと。昔は自分でやりたいことを決めてそこで就職に行くっていうと、学生たちはそれをロジカルじゃないって言うんですね。自分がやりたいとかやりたくないっていう以前に、相手が採ってくれなかったら、やりたいかどうか考えてもしょうがないので、方向性を決めずにまず内定をいっぱい取りに行く。きわめて幅広い業界を対象に内定を取りに行くらしいんです。
業界を絞るタイプは少数派なんだよね。多数派は、業界絞らない。
絞らない、絞らない。ハーバート・サイモン* の世界なんです。まず選択肢を揃えるんですよ。その選択肢の中の効用関数をちゃんと計算して、その中からもっとも高いものを選ぶ。極めて合理的なんですけど、結果としてそれで面白い業界に行くかというと・・・彼ら自身は自分の価値観で自分を納得させられないので、効用関数の選び方が他者と共有できるというか、極めて客観的で誰にでも通用することになる。給与が高いとか人気企業とかいうことで自分の関数を計算することになるから、結局ありがちなものになって、最終的には自分で選べなくなる。
*ハーバート・サイモン : 政治学者・経営学者。組織の経営行動と意思決定に関する研究などで有名。
本当に買い物するように合理的行動をとっているんだけど、一番肝心な自分のモノサシを作りきれていない。合理的なプロセスだけど自分にとって合理的な基準がないから、生まれたアンサー、結果、行動、選択は本人的にとって必ずしも合理的ではないんだよね。だから結果的に、合理的に行動したはずなのに不本意な結果になって離職退職するっていう学生が減らないんだよね。
減らないよね。
なんでそれが合理的にならないかっていうと、彼らは昔の経済学的に言うと、いわゆる完全情報を前提にして動いているんですね。つまり今後自分の価値観が変わるしかもしれないとか、知識が増えていくかもしれないとか、自分が知らない世界が広がっていくっていう前提がなくて、自分の知っている世界がイコール世界であるという前提で動く。でも (実際は) そんなことはなくて、生きていて仕事をしていくうちに全然違った、自分が気づかなかった世界の話を聞いたり、世界がどんどん広がっていくと、おや?ってことになって。もう一度計算しなおすと、やっぱり違うと。
つまり完全情報を前提としていて、完全に将来が予測できて、その中で合理的な選択するという行動。いま流行りのバックキャスティングの方法なんですよね。3年後とか5年後についての自分を想定をするんだけど、いま完全情報を持っていて、5年後のことが完全にわかるという前提だから。
世界が広がっていく感覚だとか、今まで自分が興味がなかったものに興味が広がっていくとか、全然関係ない面白い人とつながって自分の交友関係が広がって、見えてる世界が広がっていくっていう学び方とか、それをどうも学生自身がイメージできていない気がするんですね。
別の言い方をすると、自分を取り巻く世界はあまり変わらないと思っている。
そう、そうなんです。
そして自分を変える、自分が変わるということもあまり思っていないので、結局、与えられた状況と固定的な自分のベストマッチを探しているわけ。合わなければ次っていうことで、もう捨てて別の買い物に行くしかない。
経営の研究の中でジョブ・クラフティングってあるじゃないですか。ああいうふうに生き延びたら、サバイバルしたらいいのに。組織とか世界と自分の関係なんていうものは、なんとか折り合いつけてサバイバルするしかないと思うんだけど。自分が変わることで、世界がちょっと変わったりするじゃないですか。そういう物の見方、マインドセットってないのかなって。
学生たちは非常に閉ざされた世界に生きているということを、様々な分野の教育関係者が気づいてきてて。例えばSFC (慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス) でPCカンファレンスやったのいつでしたっけ。
(2017年なので) 2年前ですね。
2年前か。あの時にカタリバの今村亮さんにワークショップをやってもらって、その今村さんがこの間カフェゼミに来てもらって言ってたのはまさにそうで。
特に地方の高校生は、完全に閉ざされた世界に生きている。僕のゼミ生も奇しくも言っていたんですが、大学生を生で見たことなかったから大学生がいるなんていうことも考えてなかった、と。本当に閉ざされた世界で、イヤな子に出会っても自分はそこで耐えていかなくちゃいけないとか、嫌な言葉ですけどスクールカーストの中で自分は生きていくとか思っていた。それが、今村さんたちのカタリバで大学生が来たり、先生でも友達でもない人に会うことで、ふっと世界が広がっていく感覚を見せると子どもたちが変わっていく。
広がった瞬間の経験とか、狭い世界から広い世界に1歩でも出た経験が、ちょっとずつできてくると、自分がいま生きている世界だけじゃないんだなっていうことがわかってきた。
僕はカタリバはね、その時にすごく共感できて、あぁ面白い活動だなと思って。
カタリバは、やっぱり地方の高校生・中学生たちにとっては、外部から来ていることに意味があるんでしょうね。
はい。
いま私は京都市に住んでいて、こういう都会に住んでいると、日常の中に多様性とかサプライズとかがけっこう埋め込まれているので、その日常生活の中での経験学習で、繰り返し繰り返し、自分が思っていたことが否定されるような出会いが少なからずある。もちろん、それを捉えられるかどうかとか、それを受け止めるかどうかはまた本人のアプローチの問題もあるんだけど、そういう環境があるなぁと思うんです。
でも自分が育った愛知県の田舎だと本当に選択肢が狭くて、出会える大人も少なくて。私は中学校から名古屋の高校に行った時にすごく衝撃を受けたんですね。世界が100倍ぐらい広がったような気がした。京都大学に行ったときよりも、そっちの方がインパクトは大きかったです。名古屋の高校から京都大学に行っても多少変人率が高まっているだけで、名古屋の高校も進学校で面白い奴いっぱいいたので。歴代天皇の名前を全部言えるやつとか、そういうのがいっぱいいた。 (高校から大学は) 延長線上だったので、そっちはあまりショックは受けなかったんです。ショックを受けたのは中学から高校ですよ。
そういう意味で言うと、都会っていうものの持っている学習環境の成熟っていうかね、これが本当に結果的にものすごく差をつけている。
大学に入ってからも、学生たちに越境してもらうという感じで (僕のゼミは) やっているんですけど、僕が思う「越境」は、人材育成で考えられている「越境学習」とは結構違ってるんですね。
いわゆる「越境学習」は、空間的な意味で外に出る、学校の外とか組織の外に出て学ぶっていうのを重要視してるんですけども。なんでそれが重要なのかっていうことに関して、人材育成の人たちは、結局、組織のパフォーマンスを上げたり、人材として成長するには、組織の中だけで学んでるんじゃダメで、組織の外で学ぶことで効果が上がるという言い方をしてるんです。
でも僕がゼミでやっている「越境」っていうのは、「興味を広げるため」って1本に絞った言い方をしちゃっているんですね。少し大胆な言い方をすると、越境を学習の対語として使っているんです。つまり「学習ではなくて越境だ」という言い方をしているんですね。人材育成でよく言われる「越境学習」っていう言葉を僕は言わない。それはちょっと矛盾している気がするというか。
この場合、学習って何だと僕は思っているのかというと、熟達とイコールで考えているんですね。つまり、知識が増えたりスキルがついたりパフォーマンスが上がったりして、ある領域で垂直的に成長していくというイメージが「学習」。それを熟達と言うんだと思うんです。
それに対して「越境」は横に学んでいくというか、今まで興味がなかったものに興味が広がっていくとか、全然知らなかった分野のことを知るとか、価値観が変わっていくとか。これは熟達とは違って上手くなるわけではないし、知識が増えるわけでもないんだけど、世界が広がっていったり世界観が変わっていったりする、横の広がり。
エンゲストローム* っていう研究者は、horizontal development と vertical development っていう概念を使ってる。いわゆる熟達は vertical に development するんだと。それに対して horizontal な development ってのは、教育学者が今までちゃんと考えてきてないと。どうやってある領域で熟達していくかっていうのは、教育工学を中心に相当研究されているけれども、なんで関心が広がるのかとか、なんで今まで興味のなかったことに目が向き出すのかというのも、発達の重要な領域なんだけど、偶然や本人に任せていて。それをきちんと考える必要があるんじゃないか、っていうことを言ってるんですね。
*エンゲストローム : 活動理論や拡張的学習などの概念を提唱する研究者。
いま学生はすごく狭い領域、自分の知っている領域だけで考えようとしているから、大学生に必要なのは、どうやって horizontal に自分の世界を広げていくのかっていう術とか手がかりみたいなものじゃないかな。それを与えてあげて、自分の世界を広げていくことができる学生が増えていけば良いなと思っている。
だから、他の先生たちには怒られるかもしれませんけど、実は長岡ゼミでは vertical な方向に向けた指導はほとんどしていない。それをやらずに horizontal な方向に向けて、どうやって自分の世界を広げていくかを考えようということなんです。
なんでこう考えるようになったかって言うと、PBL (Problem Based Learning) とかアクティブラーニングって、コモディティ化されてきて、いい教育プログラムがどこかしこにいっぱいあって、ゼミでやらなくても学生たちが自分で見つけてきて学べるようになっている気がするんです。
でも、大学教育もそうだしビジネス領域でも、やはり vertical な方向に成長することばかりを考えているんで、 horizontal な方向に何んとかチャレンジしようとする学生たちを理解して、支援して、そういう試行錯誤を認めてあげる場がないと思って、作ろうとしたっていうのが最初のきっかけですかね。
受験を経て大学まで来た子は、基本的には教えなくても vertical な方向に成長しようという意志だとか、エネルギーがかなり強いので、僕がいちいちそこで「vertical に学べ」とは言わなくても、自分からそうやっちゃうと。
これが今の時代だよね。もうまさに、小学校中学校の学校教育もそうだし親もそうだし。社会が目的・目標を持ってそれに向けてやっていく。とにかくハイデッガーとかいろんな哲学者が、人間は世界を目的手段体系で見てるじゃないかと言ってるけど、それがもう染み付いちゃってる、ものすごく機能主義的な物の見方が第一原理になっているというのはありますよね。
おっしゃるとおり。だから、不安になって「何も教えていないのはダメなんじゃないか」とか「そうは言っても vertical な学びも大切ですよね」とか言ってくる人が時々いるんですけど、そんなことは特に気にしなくても、世間にはそういう方向へのエネルギーが強いので。僕が vertical な学びをゼロにしたいっていくら頑張っても、そんなの実現しないから心配しなくていい。むしろもう徹底的に horizontal に行けって。むしろ、そう言わないことによって狭い世界の中だけで生きてしまうことの方が怖い。
そういう世界で難しいのは、ビジネスパーソンに特に聞かれることなんですけど、どうして興味のない世界に行くべきなのかということ。なぜ行くのかという理由付けが、目的思考が強い人にとってはむちゃくちゃな悩みの種なんですよ。行動を起こすのに、自分を説得する理由が必要だとむちゃくちゃ強く思ってる。
ビジネスパーソンは特にそうですね。本来はマネージャークラスになると、もういろんな領域のことを知らなきゃいけないのに、手当たり次第に行こうとしないし、誰かに推薦してもらわないと行けないので、知識の範囲がすごく狭い。自分が納得できる領域にしか行かないので。本人は越境しているつもりでも、他人から見るとかなり狭い範囲にしか行ってない。目的をコスパよく達成したい人にとって、自分の関心外の領域に越境していくのは難しい。
僕のゼミでも「直感と好奇心で動け」って言ってるんですけど、それで「楽しい」と思える学生は全然苦労しないんです。でも「失敗したらどうするんですか、先生?」という子にとって、直感と好奇心で動くのは難しいですよね。
興味がなきゃ動けないのは人間だから当然なのに、興味のない領域に行けるのはなぜかって言うと、ひとつのきっかけになるのは人への関心です。この人に会いたいとか、面白い人たちのネットワークに参加したいとかの動機から動き出すことがあるってことが、やってみて分かった。
例えばCIECなんかで特に感じるんですけど、テーマにはたいして興味ないけど何か面白い人だからちょっと話聞いてみようかな、と思って話しかけたら楽しかった。なんかこう、自分の世界を広げることを誘発していくネットワークというのがあって、そんなネットワークをうまく作って、そのネットワークの中の人たちと付き合っていると、自然と越境できるというか。自分の関心以外のことについても面白い情報が入ってくる。CIEC、けっこうそういうところですよね。
だから、学生たちはあまり合目的的に越境するんじゃなくて、面白い人とのネットワークを作ろうって思ってほしくて、「あまり深く考えず、面白い人に会いに行けばいい」と言っていて。
リンダ・グラットン* が「ワークシフト」で言っているんですね。三つの人間関係が必要だと。
一つ目はプロジェクトのメンバーとしての同志とのネットワーク。二つ目は自分の心を癒してくれるような安らぎのネットワーク。三つ目として、そんなに親しくはなくてプロジェクトをやる同志のようなレベルじゃないけども、楽しく会話ができるような、自分の世界を広げてくれるネットワーク。
その三つ目をビッグアイディアクラウドと言っている。そのクラウドは多分イメージとしてFacebookの「友達」ぐらいの感じなんですよ。このネットワークでは、自分にとって全然興味ないことなんかも含んだ話が飛び交っていて。でも時々、ちょっと面白いなと思う情報に出会ったり、こんな話あるよと声かけられて面白そうと思って、ちょっと話聞かせてよと言ったりしながら、自然と興味の範囲が広がっていく。
*リンダ・グラットン : ロンドン・ビジネススクール教授で経営組織論の専門家。「ワーク・シフト」や「ライフ・シフト」の著者。
今の大学生はかなり合目的的に動いていて関心領域が狭いので、ビッグアイディアクラウドのような関係をあまり大切だって思ってないんですよね。でも、学生たちにしつこく言って、ビッグアイディアクラウドのようなネットワークを広げていって、Facebook上で魅力的な人が発信する情報に触れたり、全然違う領域のテーマに関心を持っている他大学生と情報交換すると、少しづつ変わっていく。キャリア論の Planned Happenstance じゃないですけど、偶発を誘発できるような関係が越境を通じてできていくと、後は自然とその関係を続けていけば、知らず知らずのうちにいろんな領域に興味を持つようになる。今ゼミではそんな状態を目指してやっている感じですかね。
それは本当に広がっているのか、広がってないのかというのが、本当に自分に当てはめても気になるところですけどね。
つまりFacebookをやることで、いろんな人がFacebook上で紹介リンクを張るじゃないですか。それがほんとに今では日本経済新聞読むより面白いという、知人友人フィルタリングですよね。そうなってしまっているのは、私がそういう知人友人がいるからでもある。
その状況にしても、自分の好みの人だけをTwitterでフォローすることに近い状態になりかねないので、これはこれで「関心でしか人は動けないのに関心で行くと狭まってしまう」というパラドックスと言いますか、ジレンマは中々に悩ましい話で。
だから、意識的に関心がない人たちと出会える場みたいな、近年でいうとやっぱり、いろんな所にコワーキングスペースが生まれているじゃないですか。
コワーキングスペースみたいな、あるいはスターバックスのようなサードプレイスという、リンダ・グラットンが言う三つ目の関係は、20世紀ではあんまり無かったわけじゃないけど、そんなに重要性に注目されてこなかった、21世紀の新しい求められる人間関係のデザインだなと思います。
そうですね。CIECの20周年記念シンポジウムで鈴木寛さんが話していた、これからは予測できない時代だと。そういう時代には、それこそバックキャスティング的な発想はふさわしくない。予測した未来に向かって目的的に動くんじゃなくて、偶然を誘発するような関係を築き、予測不可能な未来に柔軟に対応するというのが重要だと思いますよね。「将来うまくいくためには、正確な予測と、予測を忠実に実行する熟達的な力が必要なんだ」っていう発想から「もう将来が予測できないから、偶発に柔軟に対応して行くような関係を築いていく」という方向に発想を転換していくべき。
それともう一つ。偶然を誘発していくサードプレイス的な場をうまく機能させているのは、ソーシャルな意識の広がりだと思います。個人的な損得勘定に基づく活動や、組織の利潤最大化を目指すっていう意識が、相対的に弱くなってきている。徹底した合理主義や極端な自己責任論を少し緩めて、あなたと私の共通の利益を求めましょうとか、社会にとって良いことをやりましょうとかいう意識が広がりつつある。もちろん、経済的合理性は重要なんだけど、「利潤最大化」というレベルまでの突き詰めた発想はやめたという感じだと思うんですね。
利潤最大化という理念は、利潤に直結しない事は徹底的に削るという妥協のない合理主義。それは多くの成果をもたらしたが余裕を生まない。そこで、利潤は重要だけれども、「最大化」までは徹底しない、余裕を持った発想ができるようになると、損得勘定に振り回されたり、短期的な目的達成に囚われることなく、直感や好奇心で動こうという余裕が芽生えるようになる。サードプレイス的な場もでてきて、その結果、「わたし」の目的に過度に固執しないで、「あなたとわたし」の目的達成をめざす方が、むしろ一人ひとりのことも上手くいく、という感覚が共有されるようになってきたのかなと思いますね。
僕のゼミのもう一つの特徴として、プロジェクトをやらないんですよ。ゼロ。PBLやらない。アクティブラーニングやらない。
僕、産能大 (産業能率大学) にいたころはアクティブラーニングとかPBLとかガンガン、CIECでもそういう発表ばかりしてたんです。
でもなんで止めたかっていうと、やっぱり大学でやっても10週間くらいなんですよね、プロジェクトが。10週間じゃ試行錯誤できない気がしてきたんです。学生たちは賢いから、10週間で答えを出そうとする。10週間で (途中で) 方向を変えるなんて、そんなリスキーなことはやらないんですよ。10週間後にどこに到達すればいいかっていう到達目標を決めて、うまく行くように微調整をしながら行くっていう学びになっちゃうんですよね。
それがじゃあ1年になると試行錯誤するのかっていうと、しないんです。学生たちはやっぱり合理的で、ちゃんと教育を受けてきてるから、到達目標があってそこにどうやっていくかっていうのを、ものすごくうまく計算できる。僕らがいくら到達目標をぼやかしても、ヒアリングの中から先生が目指してるレベルをなんとなく汲み出してきて、じゃあここら辺を目指すにはこういうふうにやれば良いんだなってなっちゃうんですよ。
それをやめて、本当に失敗してもいいやと思って試行錯誤から学ぶには、もうゴールは決めないと。
やっぱり直感で動けるのは「失敗しても良い」と思ってるからで。試行錯誤をするとか大きな方向転換するとかっていう経験をさせるには、もう「成果なんか見ないから好きにやれ。そのかわり、あなたがやってることはちゃんと見てるから」っていう環境を2年くらいの長期間確保してあげないと、ちょっと頭の良い子ならやらないよねっていう気がするんですよ。
もうCIECでも授業でも企業のインターンシップでもNPOでも、良いPBLとか良いアクティブラーニングはいろいろできてるんで、そんな状況の中で、ゼミが1個新しいPBLを付け加えてもあんまり、オッカムの剃刀* じゃないですけども、1個増やしてもしょうがないんで。
それを意識してゼミでは、逆のことをやります。結果じゃなくて、プロセスをずっと見ててあげるから「失敗しちゃった」って言ってもいいし「行き詰っちゃった」なら行き詰った話をしようよっていう。うまくいくかどうかわからないですけど、ある意味実験的にやり出しちゃったって感じですかね。
*オッカムの剃刀 : 「ある事柄を説明するために必要以上に多くの仮定を用いるべきではない」という考え方。哲学者オッカムが論理的思考として多用したことにちなむ。
一般にプロジェクトっていうと、やっぱりちゃんと結果ださなきゃいけない、結果出そうとすると、もうリスクを回避してこの期間内でお行儀良く進める、というふうに、やっぱりそこにある種の目的志向、合理的にやってしまうというのがある。本来「予測不可能な時代に生きてる」ということを味わわなければいけないのに、予測可能な範囲、制御可能な所に落とし込んでしまう。それでは、ここで学んでほしいテーマが完全に脱落する、という自覚ですよね。
はい。でも、こういう事ができるのは、ある意味アクティブラーニングだとかPBLとかがすごく普及してきたからで。ゼミで越境ばっかりやってて大丈夫なんですかと言われるんだけど、ゼミ以外の場にはかなり質の良いPBLのプログラムも多くあるから、ゼミでのPBL経験を1個付け加えなくても学生たちは十分成長できるという状況にあるのは、かなり確かだと思う。
他に機会がありますものね。
はい。僕がCIECに入ったころ、僕がアクティブラーニングやってたころは (そういうものが) ないんですもの。
ないんです。ほんとに座学型が大半で、自分たちで発表するというのが珍しかったですものね。そもそもね。
だから特に今の時代、学生は自然とそういう合理的な発想になるし、サポートする環境は山ほどあるんで、そうじゃないのを強調しすぎても、しすぎるということはないと思ったんです。
インタビューを終えた長岡健さん (左) と若林靖永CIEC会長 (右)